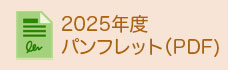-
★案内★12/14講演会開催! インクルーシブな社会を目指すための学習会では、12月14日に下記のとおり講演会を開催いたします。みなさまのご参加をお待ちしております。 日時:12月14日(日) 13:30~16:30 場所:大和市ポラリスRoom3(最寄り駅:小田急江ノ島線・東急田園都市線「中央林間駅」) テーマ:「授業デザインからインクルーシブを考える~デジタルシチズンシップの取り組み~」 講師:草原 和博 氏(広島大学教授) 12/14学習会チラシ(←PDFダウンロード) ◆講演主旨◆ 本学習会のテーマである「インクルーシブな社会を目指す」取り組みの中では、多様な市民の包摂や対話の重要性がしばしば議論されてきました。それを踏まえ、この先をもう少し進められないか、社会課題について対話を繰り広げていくことはできないかと考えてきました。その中で「デジタルシチズンシップ構想」と出会いました。そこに何かヒントはないか、それを考えるために、広島から講師をお招きすることにしました! ◆デジタルシチズンシップ構想とは◆ 「新しい公教育の姿をカタチにする」という目的を掲げるDCC(デジタルシチズンシップ構想)は、東広島市で実践研究が行われています。 求めている学びの姿は、次の5つです。 ①規模の異なる学校の協働、②公共的課題の対話、③越境する教室空間、 ④デジタルによる柔軟な結合、⑤多様な市民の包摂 授業づくりの観点でも、とても有意義なお話が聞けそうです! どうぞご参加ください! ※資料代:500円(当日会場で集めます) 問い合わせ先:インクルーシブな社会を目指す学習会 (担当:柿本 kakimotogeronimo315@gmail.com)
学校支援活動
-
夏休みの宿題 ※しばらくエステレージャ教室の報告が滞っておりました。 もう少し頻繁に教室の様子をお伝えできるようにしたいと考えております。 【2025年8月9日 エステレージャ教室の記録より】 中学2年生のS君が久しぶりに教室に顔を出しました。 聞けば、今日はサッカーの練習がないのだそうです。このところものすごい暑さなので、大変ではないのかと尋ねると、さすがに「大変です」と苦笑いをしていました。そして昨日は練習があったのだけれど、暑すぎたのと体調を崩したので休みました、とも言っていました。 そんなS君ですが、今日は教室にたくさんの宿題を持ってきました。何をするのかと尋ねると国語のワークを持ち出してきました。まずは漢字の語句の意味調べから取り掛かります。「どれどれ・・・」と横からのぞき込むと、なかなか難しい語句を調べなければなりません。例えば「精密」、「口実」、「極端」、「蛇行」・・・。問題を見て、ちょっとびっくりしてしまいました。 実はS君が来日したのはそんなに昔のことではありません。もちろん小学校レベルの漢字も身についているわけではありません。そんなS君にとって、「精密」やら「蛇行」やらの意味を調べて書くということが、どれほどハードルが高いことであるか。 思わず「これ、やらなくてもいいんじゃない?」と口にすると、「いや、これをやっていかないと、サッカーの練習に参加させてもらえないんです」とS君。 ・・・う~ん。。。本当は難しい宿題よりも、彼の実力に合わせて小学校の漢字からじっくりと学ばせていきたいところなのですが、部活関係のしがらみもあるのか・・・・ こうなったら、ワークに付いている解答を見ながら、赤ペンで(解答を見ながら書き写した時は赤ペンで書くのがルールなのだそうです)書き写すのを見守るしかないんです。彼がその言葉の意味をどれだけ理解できているのか、いや多分、まったく理解できないまま、書き写していくしかないのです。きっとこういうことは国語に限らず、すべての教科で普通に見られることだと思います。これまでもこういうケースを幾度となく目にしてきました。 宿題って何だろう、学習って何だろう、と 強く考えさせられた酷暑の一コマでした。(TH)
外国人支援・こども支援活動
-
No.71現在の学校の構造 Ed.ベンだよりNo.71が発行されました。 今回のEd.ベンだよりのタイトルは「現在の学校の重層化した構造について」です。 Ed.ベンだよりNo.71ダウンロード 新政権が発足しました。 「経済、経済」と、お金を巡る事柄、それも目先の利益や景気の追求が強調され、ゆっくりと考えることすらままならない中で、一層混迷した社会に突き進んでいるように思われます。 日本という国のあり方が大きく変えられてしまおうとする今日、これまでの教育と学校のあり方をもう一度たどりながら、今の学校が抱える問題のルーツを振り返る必要があるのではないかと思います。 その際、今回のEd.ベンだよりはとても良い道しるべになってくれるものと思います。是非お読みください。 また、12月中に開催されるEd.ベンチャーの研究会、学習会の案内も掲載されています。みなさま是非ご参加ください。
Ed.ベンだよりPDF
-
2025年11月28日 Ed.ベン便り No.71現在の学校の構造
-
2025年11月13日 インクルーシブ社会を目指す学習会 ★案内★12/14講演会開催!
-
事例研究会は、外国にルーツを持つ子どもたちの具体的な事例を通して、かれらの背景にある事情や問題を読み解く力をつけていくというねらいで開催しています。9月・10月は連続した内容での研究会となりましたので、あわせて報告します。 【事例研究会9月10月報告】 日時:2025年9月17日(水)、10月16日(木)いずれも19:00~21:00 オンライン(Zoom) 事例:「いろいろな課題を抱える子どもの事例」 事例提供:大和市内中学校教諭 参加者:9月17日:6名、10月16日:5名 9月10月は、連続した内容での研究会となりました。 9月は、中学校の先生から中国ルーツの子どもの事例を提供していただきました。小学校では持ち物や提出物が揃わなかったり、宿題をやってこなかったりといったことがあり、中学生になってからはクラスのみんなから嫌なことを言われると担任に相談を持ちかけ、体調不良を理由に保健室に毎日通っている子どもの様子が報告されました。報告を受けての協議では、学校は子どもを育てる場で、子どもの意思表明を保障していくことが重要であることを確認しました。アドバイザーの先生からは、子どもとの会話を通して、子どもが選択して納得する場面をどう作っていくかが重要であること、子どもとの会話から格差を確認してその格差を埋めるために何をするのかを探し、子どもの資源を増やしていくことが重要であることというアドバイスがありました。そして、事例で紹介された生徒との会話を深めて子どもの背景や置かれている状況、子どもの思いなどをより詳しく把握する必要があることが確認されました。 10月は、9月の協議を受けて当該生徒の話を聞き取った結果を報告していただきました。子どもと会話を重ねる中で、9月の報告では分からなかった子どもの背景がより明らかになったという報告とともに、話を聞いたことで子どもとの関係がより深まっていったこと、そして子ども自身の学校生活が上向きになっていることなどが報告されました。今回は子どもとの対話についての協議が中心となりました。協議では、対話することの意義は何なのか、話を聞くポイントはどんなことかといったことが話題となりました。アドバイザーの先生からは、対話の意義には、話すことを通して自分を客観視することにつながること、問われることで言葉を獲得し認識が豊かになっていくことというお話がありました。また、対話をしていて子どもが「分からない」という状況が出てきた時には、言葉がないから分からないのであるから聞き手が言葉を置いていくことで言葉の獲得につながっていくとのアドバイスもありました。 外国人の子ども理解のための学習会では、昨年度「対話」をテーマにした学習をしました。9月と10月の事例研究会は昨年度のテーマにつながる内容となりました。聞き手が対話の持つ意義を理解したうえで子どもとの対話の時間を作り出すことが必要だと感じます。今、学校は先生も子どももとても忙しい場所になっていて、対話する時間が取りづらいという面があるかと思います。外国ルーツの子どもにとっては、対話をすることは自分が受け入れられている、認められているという安心感を持てることに繋がり、言葉を獲得したり知識を増やしたり、資源を増やしたりする機会でもあることを今回の研究会を通して再確認しました。昨年度のテーマが再び取り上げられたということから、外国ルーツの子どもにとって、対話をするということが重要な支援の形だということだからです。国語や社会科といった教科学習の知識をつけることだけに支援が向くのではなく、子どもの資源を増やしていくための支援を意識して子どもと向き合うことが必要だと感じます。
2025年10月26日 外国人の子ども理解の学習会 【報告】9・10月事例研究会
-
2025年10月12日 Ed.ベン便り No.70「平和」のゆくえ
-
2025年10月09日 お薦めの書籍・文献 東京大空襲
-
2025年09月09日 お薦めの書籍・文献 なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか
-
※しばらくエステレージャ教室の報告が滞っておりました。 もう少し頻繁に教室の様子をお伝えできるようにしたいと考えております。 【2025年8月9日 エステレージャ教室の記録より】 中学2年生のS君が久しぶりに教室に顔を出しました。 聞けば、今日はサッカーの練習がないのだそうです。このところものすごい暑さなので、大変ではないのかと尋ねると、さすがに「大変です」と苦笑いをしていました。そして昨日は練習があったのだけれど、暑すぎたのと体調を崩したので休みました、とも言っていました。 そんなS君ですが、今日は教室にたくさんの宿題を持ってきました。何をするのかと尋ねると国語のワークを持ち出してきました。まずは漢字の語句の意味調べから取り掛かります。「どれどれ・・・」と横からのぞき込むと、なかなか難しい語句を調べなければなりません。例えば「精密」、「口実」、「極端」、「蛇行」・・・。問題を見て、ちょっとびっくりしてしまいました。 実はS君が来日したのはそんなに昔のことではありません。もちろん小学校レベルの漢字も身についているわけではありません。そんなS君にとって、「精密」やら「蛇行」やらの意味を調べて書くということが、どれほどハードルが高いことであるか。 思わず「これ、やらなくてもいいんじゃない?」と口にすると、「いや、これをやっていかないと、サッカーの練習に参加させてもらえないんです」とS君。 ・・・う~ん。。。本当は難しい宿題よりも、彼の実力に合わせて小学校の漢字からじっくりと学ばせていきたいところなのですが、部活関係のしがらみもあるのか・・・・ こうなったら、ワークに付いている解答を見ながら、赤ペンで(解答を見ながら書き写した時は赤ペンで書くのがルールなのだそうです)書き写すのを見守るしかないんです。彼がその言葉の意味をどれだけ理解できているのか、いや多分、まったく理解できないまま、書き写していくしかないのです。きっとこういうことは国語に限らず、すべての教科で普通に見られることだと思います。これまでもこういうケースを幾度となく目にしてきました。 宿題って何だろう、学習って何だろう、と 強く考えさせられた酷暑の一コマでした。(TH)
2025年08月10日 子どもの居場所・学習教室 夏休みの宿題
-
2025年07月11日 Ed.ベン便り No.69教育の役割とは
-
2025年06月09日 お薦めの書籍・文献 ガザ日記:ジェノサイドの記録
-
2025年06月05日 Ed.ベン便り No.68教育の役割を模索する
-
2025年05月15日 お薦めの書籍・文献 この計画はひみつです
-
授業研究会報告:第1回(3月29日) 参加者11名(対面のみ) 2025年度の授業研究会の一つの柱は、東京一極集中を促してきた高度経済成長の背後の資本主義に焦点をあてつつ、東京と地方の教育にどのような格差を生みだしてきたのか、また、その格差を解消するための道筋として、どのようなことを考えればいいのかを検討するということです。 今回は卒業論文で「脱資本主義の思想としての地方移住の可能性を考える-教育観や子育てに対する考え方に焦点を当てて-」に取り組んだ門井みなみさんに報告をお願いし、それをもとに検討を行いました。 論文に対しては、現在の学校教育が資本主義の担い手育成の装置になっていることを明言しており共感がもてた。また、地方移住に資本主義からの逃れる可能性を見出している人々がいるものの、そこで新たな価値観に出会うのではなく、再び子育ての中で資本主義に絡めとられていくことへの葛藤が見受けられることも興味深かった、という感想があがりました。 他方、今回の論文検討を通して、次の課題を検討する必要が共有されました。 ①地方に都市部とは違った価値観を見出しているとすれば、それは何であるのか、そこに学校教育を絡んでいくことができるのか。 ②人間の権利に対する考え方の浸透は、外国人労働者の処遇などの問題は見れば、地方より都市部の方が進んでいるように見えるが、この問題をどのように考えていくのか。 ③地方の中に入り込んで、都市部の資本主義とは異なる社会経済活動を構築する動きがあるとすれば、そのような具体的な事例があるのか。 以上の課題は、今後の研究会の中で深めていくことになりました。
2025年05月06日 授業研究会 【報告】3/29授業研究会
小学校のふりかえり https://t.co/uY9bmkbKPs
— Ed.ベンチャー (@edventrue) May 14, 2023